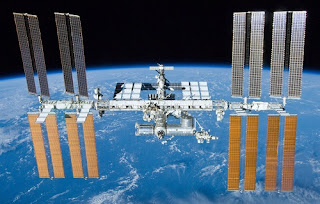こんにちは!推進部の早川です。
先日、久しぶりに外にでて、
かかみがはら航空宇宙博物館にいってきました。
すごいですね~~、様々な飛行機や設計図、模型が
広大な建屋の中にたくさん展示されていました。
色々と周っていると、宇宙コーナーに、人工衛星や
月探索機などの装置が展示されていたのですが、
よく見ると、人工衛星に金色のペラペラしたものがついています。
人工衛星などでよく見る金のペラペラ(通称金ペラ)。
見覚えは有るのですが、なんで金色である必要があるのかとか、
そもそもなんのための金ペラなのか、これは前から疑問に思っていました。
でも、そこはさすがです。
抜かりがありません。ちゃんと説明が書かれていました。
この金ペラは、サーマルブランケットといい、
過酷な温度変化から人工衛星を守る「断熱服」なんだそうです。
この断熱効果は凄まじく、太陽からの熱が人工衛星の内部に侵入することを
防ぐための膜なんだとか。
実際に手に触れて触ることができましたが、
確かに、断熱効果がすごい!(気がする!)
ものすごい薄いペラペラでしたが、実際はプラスチックフィルム「カプトン」と網状の繊維「ダクロン」を交互に10層から20層も重ねた構造になっているそうです。
すみません、中身がペラペラなのは私の方でした。
一つ知識が深まったので、これから人工衛星の映像を観るたびに
鼻高々に「これは断熱服よ!」とペラペラ言えそうです。
| ツイート |
|






.jpg)